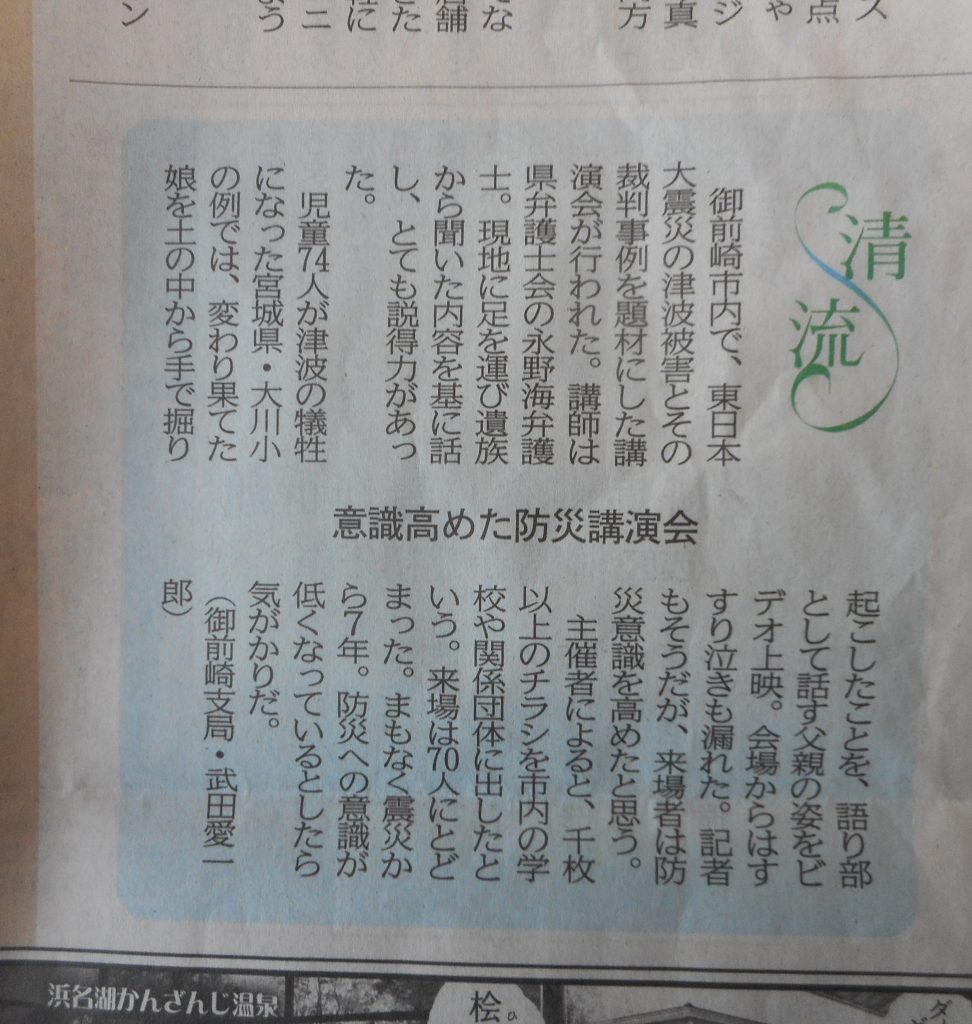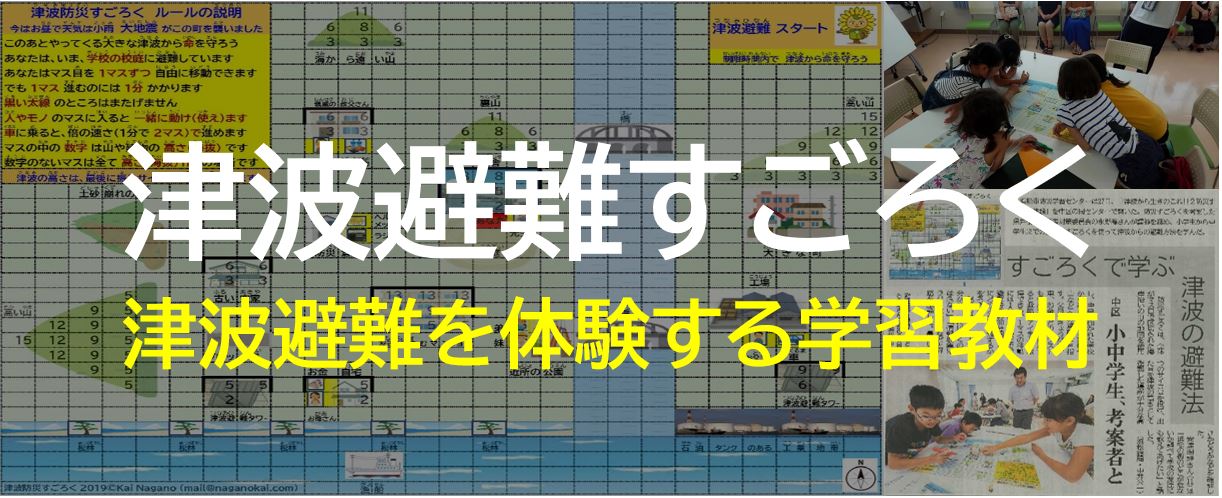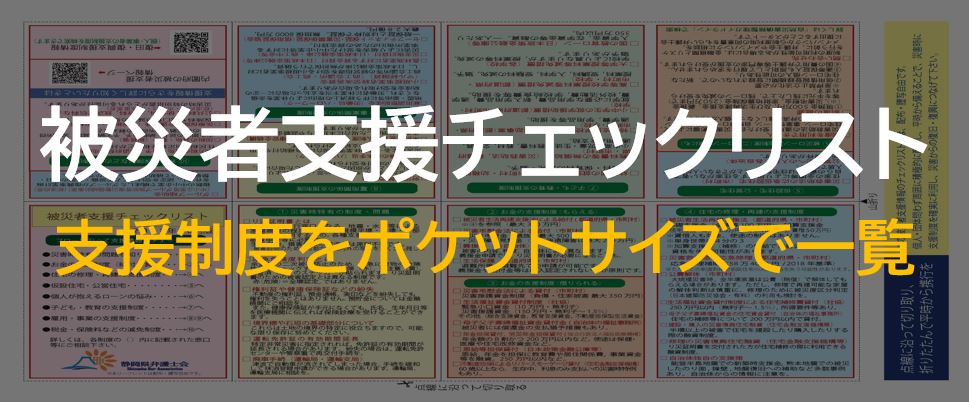(武蔵野美和さんのFacebook写真からお借りしました)

今回の津波防災の話をする機会を作り準備をしていただいた落合さんはじめ御前崎災害支援ネットワークの皆さん,本当にありがとうございました。
今回の津波防災の講演は珍しく本当に緊張しました。東は陸前高田,西は三重から,あろうことかわざわざ私なんぞの話を聞くために,車で,あるいは夜行バスや新幹線に乗って,静岡からでさえ決して近くない御前崎まで来て下さっていました。
法律問題や被災者支援のお話をするならまだしも,今回のテーマは津波防災でした。私は防災の専門家では全くなく,被災の経験すらなく,単なるどこにでもいる法律家の一人に過ぎません。
そのような人間が津波防災の話をすること自体おこがましいことだと一応自覚している中で,ましてや被災地の陸前高田からわざわざ来ていただく方に,一体何を伝えられるのだろうかと相当不安になりました。
◇
今日たくさんの方々が私ごときの話を聞きにきてくださいましたが,当たり前ですが,別に私のファンでこの場に来られているわけではありません。短いながらも私なりに多くの被災地の方やボランティアの皆さんとかかわるなかで,皆さんがどのような思いで私の話を聞きに来られているかは少しは理解しているつもりです。
みなさんは,家族のため,地域のため,社会のために少しでも尽くしたい,被災地の方は同じ犠牲を繰り返したくないという切実な思いを背景にして,1つでも2つでも学ぶことがあればと,そして学んだことを今後の活動に還元していければという思いで来られています。
そうした人たちに,何か1つでも持って帰っていただくことができるだろうか,という不安とプレッシャーを痛烈に感じたのでした。
◇
今日の2時間で何を伝えられたのか,何かを伝えられたのか答えはでませんが,私なりに,この災害が避けられない国で生きていくなかで,命を守るために最低限必要な暮らし方の作法,に関して,被災地の皆さんから教えられた,教えていただいたことを一生懸命お伝えしようと努力はしたつもりです。
1000年後のこの国に生きる人間にまで伝わる形でこの国の災害のありよう,歴史,つきあう作法を伝承していくことは,この国に生きる人間の責務ではないかと(勝手に)思っています。
そして,それが災害で失われた命を決して無駄にしないために絶対に必要なことであるとも思っています。
(藤井芳彦さんのFacebook写真からお借りしました)
今回の講演では,まず,東日本で数多く行われている津波訴訟の内容をみていただき,被災地で何が起こったのかを知っていただくことからはじめました。
日和幼稚園(石巻市) 比較対象として旧門脇小学校
大川小学校(石巻市) 同じ教訓を伝えるものとして閖上地区(名取市)
常磐山元自動車学校(山元町)
七十七銀行女川支店(女川町)
これらの津波被災事例から学ぶ教訓は膨大なものがあります。
◇
私は当初報道や判決文,各種評論などを通じてこれらの裁判例を理解していましたが,私の本業もそうであるように,何事も紙面でわかったような気持ちになるのが一番恐ろしいことです。
これらすべての現場に足を運び,幸運にもご遺族,関係者からお話が聞けた場所についてはお話をお聞きし,自分の足と,自分の目と,自分の心で感じたことだけを,率直に皆さんにお伝えしようと思いました。
◇
事前に危機意識がなく,準備を何もしていなかった現場が,大地震を目の前にするとどうなってしまうのか。
ハザードマップや防潮堤,防波堤などのハード面を頼りにした場合に何が起きるのか。
東日本大震災,これらの裁判例は雄弁に教えてくれます。
◇
そして,これらのあまりに大きすぎる犠牲を前に,われわれは何をしたらよいのでしょうか。
災害は怖いもの,津波は怖いもの,というだけの防災教育は長くは続きません。
人間の恐怖が数年で後退してしまうことは,東日本大震災から7年がたとうとする今,各地の防災の現場が証明しています。
また,津波が怖い,海が怖いでは,みな故郷を誇りに思えなくなります,地域が死んでしまいます。
◇
海沿いにいる人間だけが考えなければならない問題ではありません。
この日本列島に住む限り,地震,津波,噴火は全ての国民の生活のなかにあるものです。
たくさんのことを同時にやろうとせず,一番大事なことに絞って具体的に1歩踏み出して取り組むことが,それが大切だと思います。

(H30.2.27静岡新聞朝刊より)
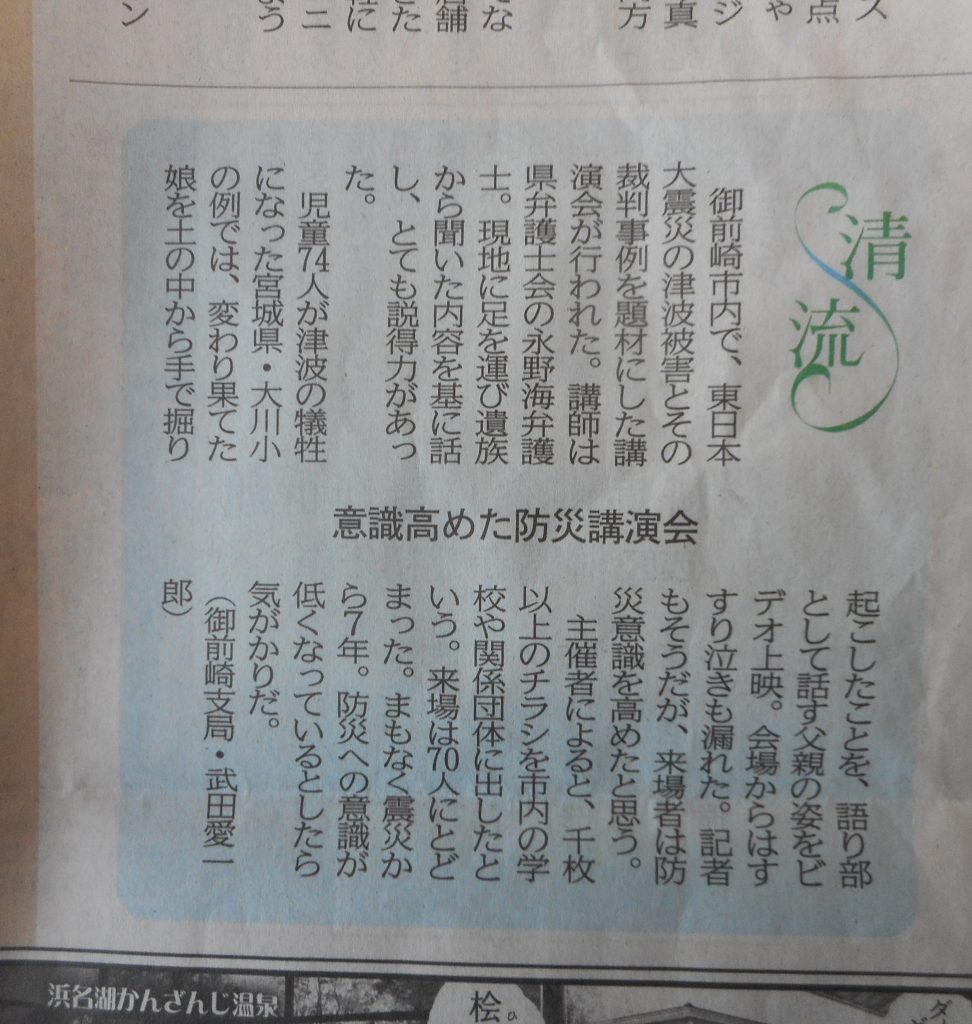
(H30.3.6静岡新聞朝刊より)
弁護士 永野 海