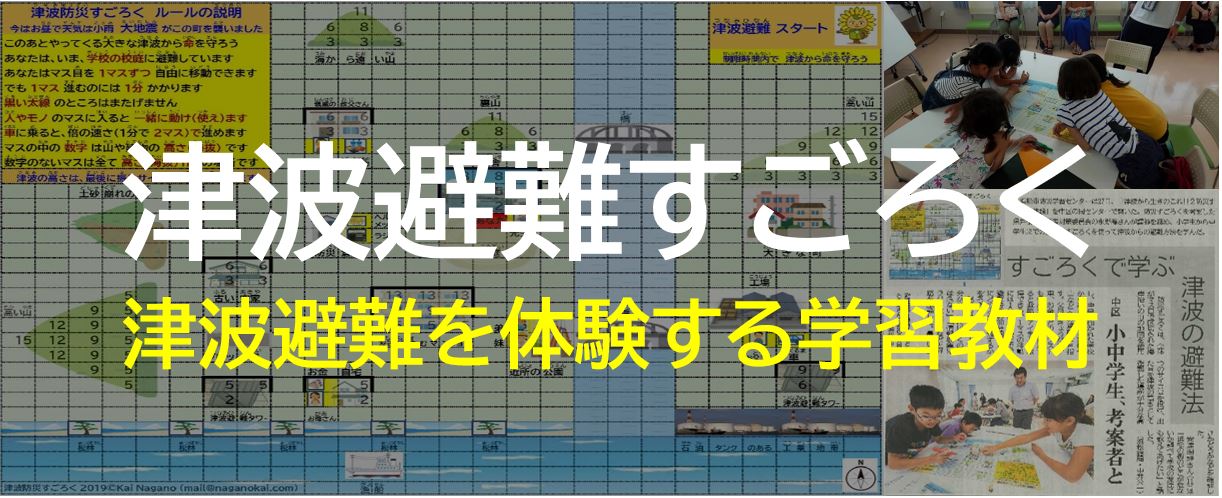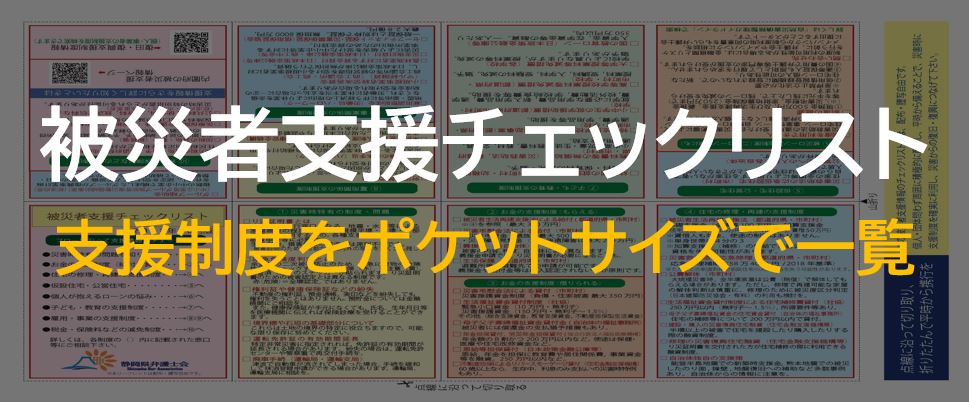大谷崩(静岡市葵区梅ヶ島) 訪問記
静岡市葵区の梅ヶ島にある大谷崩(おおやくずれ)を訪問しました。

梅ヶ島温泉にいく途中,左に入る道がありますので(大谷崩まで6kmの看板あり),そこを左折し,山道を車で登っていきます。それほど険しい道ではありませんが,そもそも現在も土砂崩れが日々発生しているエリアですので十分な注意が必要です。

写真の奥側が大谷崩れ。
写真のとおり,崩落跡の崩れた石や巨石が河原を埋め尽くしています。
なんと1億2000万立法メートルの崩落。なかなかの迫力で、ここに立ってみると自然の圧倒的な迫力にたじろいでしまいます。

工事関係者の方の話によれば、この砂防堰堤を埋めていく崩落した岩石は数年に一度のペースで取り除かれるとのことでした。


(この日静岡を訪れてくださった神戸のまち・コミュニケーションの宮定章さん、丸山弁護士とともに)
大谷崩は,300年前の宝永地震,すなわち南海トラフ地震による山体崩壊跡です。
日本三大崩れの1つで,幸田文さんの随筆「崩れ」でも有名です。

(この地域の瀬戸川層群の代表的な岩石である頁岩(けつがん)と大谷崩)
頁岩は、堆積面に沿って千枚漬けのように面白いほど簡単に割れていきます。

次の南海トラフでもきっと崩落するでしょうし、現在も日々崩落してます。
現代の砂防技術と自然との戦いの最前線の場所でもあります。

(国交省による砂防事業の説明パネル)

(幸田文「崩れ」の石碑と奥に大谷崩)
大谷嶺は、もともと糸魚川静岡構造線と笹山構造線という2つの断層に挟まれ圧砕されている上、大変な多雨地域という過酷な環境にあり、なおかつ、そこに削れやすい頁岩(粘板岩?)の山がああるわけですから、大谷崩の侵食・崩落は止みません。

1707年に起きた宝永巨大地震によるさらなる大崩落は、麓に平坦な段丘を作り、急峻な谷地形のなかに人が住める場所を提供しました。
崩落に人が巻き込まれれば自然災害と呼ばれますが、その自然現象が、人間の営みの根底を作っているわけです。

大谷崩などが日々生産する大量の土砂は、現代の安倍川下流域の住民の命を脅かすので、このエリアは「砂防ダム銀座」といえるほど現代の叡智を結集した砂防ダムが乱立しています。
砂防ダムにより下流の集落の土石流リスクや、河床上昇による洪水リスクを防いでくれていますが、他方で、河口に運ばれる石ころや砂は激減し、静岡市は今度は海岸侵食に困っています。
また、大谷崩など上流域で生み出された大量の土砂や岩石を河川が運搬し続けたからこそ、下流域には、静岡平野という扇状地が生まれ、やはりそこに人間が生活できているわけです。

また、糸魚川静岡構造線などの断層に挟まれた梅ヶ島では、最高の泉質の温泉(硫黄泉)が今日も湧き出でて、人間に恵みを与えてくれています。

防災は,形式的なものではなく,常に地球を知り自然を知った上での,自然との共生のなかでの地に足がついたものでなければいけない,そうでないと後世まで命を守るDNAとして身につくことはないと思います。
いずれにせよ,大谷崩,300年前の南海トラフ地震のすさまじさを直接肌で感じることができる,数少ない貴重な静岡の災害痕跡です。
平成29年10月訪問(H30.4、R1.12再訪追記)
静岡市清水区 弁護士 永野 海